すべての始まりは“テレビの中のラグビー”だった
冨岡剛さんの人生が大きく動き出したのは、中学生の頃。
たまたまテレビで観た早明戦。泥まみれの選手たちが全力でぶつかり合うその試合に、心をわしづかみにされたそうです。
「自分も、あの舞台に立ちたい」。
それまで野球少年だった冨岡さんは、まっすぐにラグビーという新たなフィールドへと進むことを決めたのです。
ラグビーにのめり込んだ高校時代

野球とはまるで違う体の使い方。
ぶつかり合うプレー。
戸惑いもあったけれど、「本気でぶつかる仲間たち」がいることが楽しくて、気づけば毎日のようにラグビーに夢中になっていました。
体格に恵まれていたわけではありませんが、誰よりも走り、誰よりも声を出し、努力で前に出る。
その姿勢は、後に“キング冨岡”と呼ばれる礎になっていきました。
青学ラグビー部で出会った“考える力”
青山学院大学に進学してからは、戦術を理解する“頭のラグビー”に触れます。
試合の流れを読む、相手の動きを予測する、チームを導く――
感覚だけではなく、理論でも勝負するスタイルを吸収し、“考える司令塔”として成長していきます。
神戸製鋼での出会いと“黄金期”のスタート

卒業後、神戸製鋼に入団。
そこで出会ったのが、冨岡さんが“人生で最も影響を受けた男”と語る、平尾誠二さん。
すべてが絵になるような佇まい、発する言葉の重み、グラウンドでの圧倒的な存在感。
「この人みたいになりたい」と、純粋に思わせる人だったそうです。
“お前はダイヤだ、でも磨かなければただの石だ”

ある時、平尾さんにこう言われたそうです。
「お前はダイヤの原石。でも、磨かなければただの石。ダイヤを磨けるのはダイヤしかいない」。
冨岡さんは、この言葉を今もずっと胸にしまっているそうです。
そして「絶対に磨き切ってみせる」と、日々努力を重ねてきたと語ります。
伝説の試合、“71得点”という記録
神戸製鋼の一員として出場した国立競技場の決勝で、冨岡さんは“1試合71得点”という日本記録を打ち立てます。
今なお破られていないこの記録。
その裏には、1日200本のキック練習という積み重ねがありました。誰よりも準備して、誰よりも集中する――
それが冨岡さんのラグビーの哲学でした。
“俺が欲しい時に点を取ってくれた”
平尾さんは、冨岡さんのことを“切り札”として信頼していました。
「ここぞという場面は、富岡で決める」。
そう言ってもらえたことが、何よりの誇りだったと語ります。
引退後に平尾さんから「お前は俺が欲しい時に点を取ってくれた」と言われたことは、生涯忘れられない言葉だそうです。
ホテルオークラで交わした握手
引退して数年後、冨岡さんが事業で成功していたある日。
ホテルオークラで平尾さんと再会します。ロビーの階段を上がってくる平尾さんが手を差し出し、「お前は成功すると思ってたよ」と言ってくれた。
その瞬間、涙が止まらなかったそうです。長い付き合いにも関わらず、それが“初めての握手”だったというから驚きです。
“奢られるな、後輩に返せ”の教え
冨岡さんが平尾さんにお礼をしようとして支払いを申し出た時、平尾さんは激怒。
「俺にはするな。その気持ちは、後輩に返せ」。
その言葉は、今も冨岡さんの中に強く残っているそうです。
“受けた恩は、次の世代に返す”。
それが“かっこいい大人”の条件なのかもしれません。
最後まで“かっこいい人”だった
晩年、平尾さんは闘病していましたが、最後の最後まで姿勢も美しく、振る舞いも気品に溢れていたそうです。
車椅子から立ち上がるその姿は、まるで昔と変わらないオーラを放っていたと冨岡さんは語っています。
「本当に、最後の一瞬までかっこよかった」――その言葉には、深い敬意と憧れが滲んでいました。
“かっこよさ”とは何かを教えてくれた人
平尾誠二さんは、最後まで冨岡さんに“かっこよさとは何か”を教えてくれた人だったそうです。
言葉の重み、行動の静けさ、背中で語る姿勢。
派手なことを言わずとも、誰もが尊敬する人であること。
冨岡さんは、そんな平尾さんの背中を、今でも追いかけているように思えます。
まとめ:憧れを超えて、今は“誰かの平尾誠二”に
冨岡剛さんにとって、平尾誠二さんはただの先輩ではなく、“理想のリーダー像そのもの”だったのかもしれません。
今の冨岡さんは、かつての自分が憧れたように、次の世代から憧れられる存在に。
今度は自分が誰かにとっての“平尾誠二”になる――
そんな思いで、今日も全力で生きているのではないでしょうか。
冨岡剛に関する他の記事もどうぞ



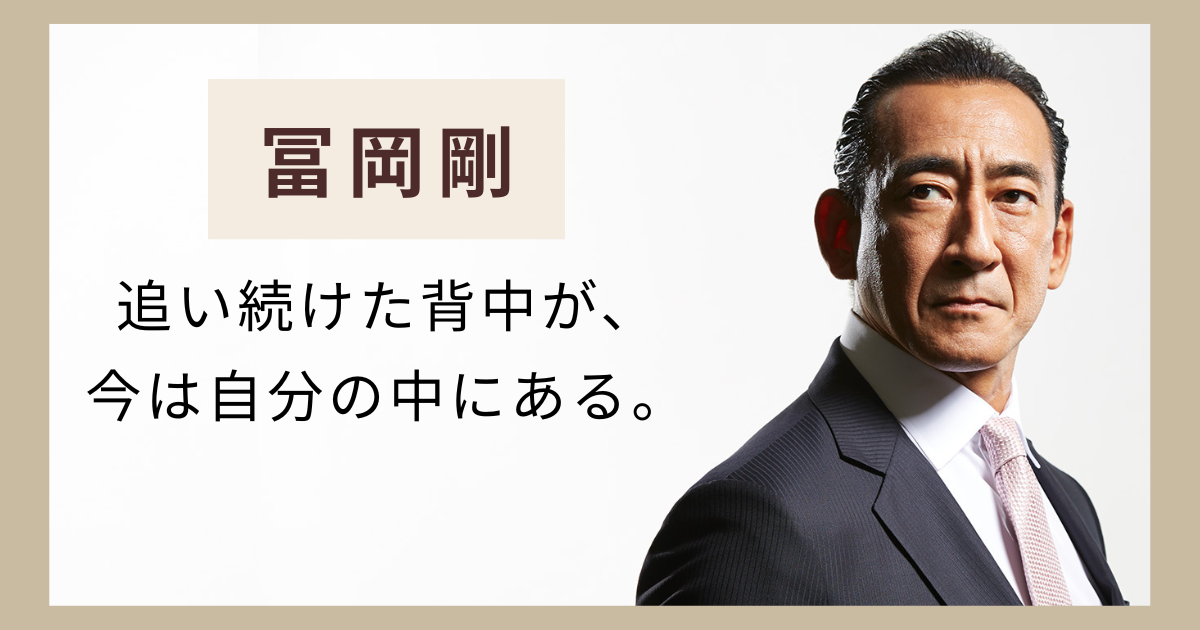
コメント